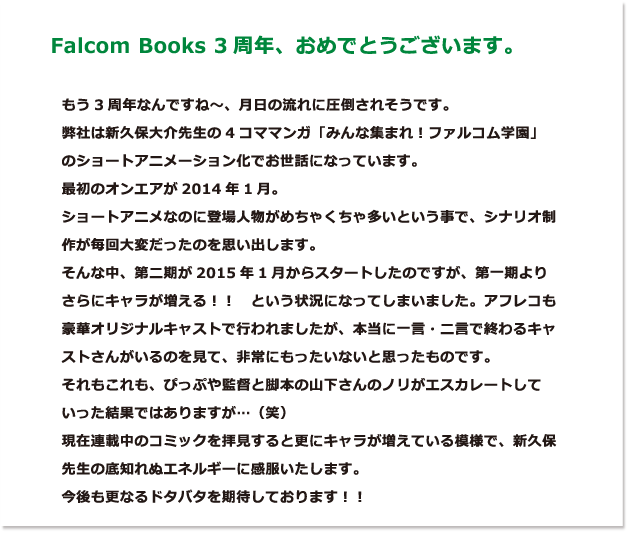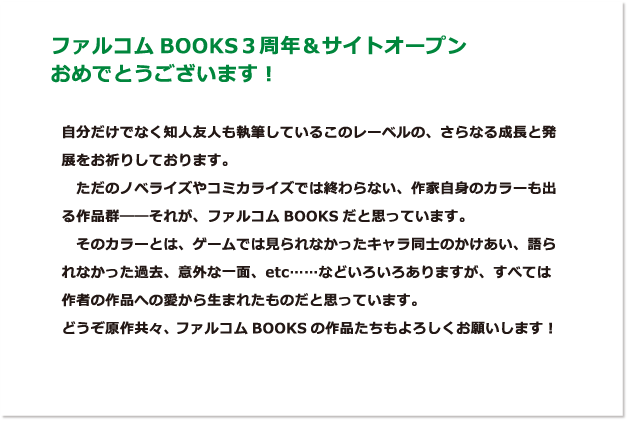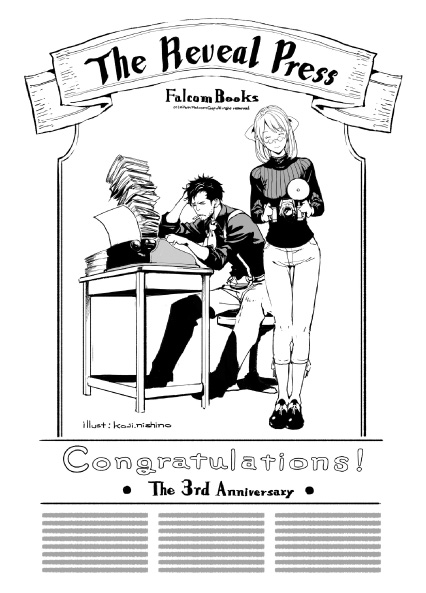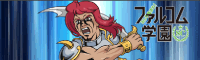第12弾 『みんな集まれ!ファルコム学園(6)』
新久保だいすけメッセージイラスト
第11弾 『英雄伝説 閃の軌跡 05』さがら梨々メッセージイラスト
第10弾 特別読み切り 英雄伝説 空の軌跡 笑顔でいてほしいから
8月10日にファルコムBOOKS最新刊『英雄伝説 空の軌跡 3 王都繚乱』が発売したことを受け、はせがわみやび先生書き下ろしの短編を掲載! エステルがアイスクリームを買いに行ったあの時、こんなことが起きていたとしたら? を描いた物語。エステルとヨシュアのこの後に起きた出来事を知っているとより感慨深くなること間違いなし! この短編の完全版は『月刊ファルコムマガジン vol.79』に掲載予定なので、そちらもあわせてチェックしてみよう!
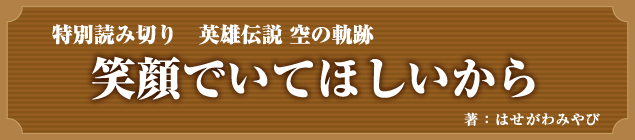
どうしよう、困った──とエステルは思った。
『入り口近くにアイスクリーム屋があったわよね。買ってくるから!』
そう言って走り出したのだけど──。
(うん。たしかにこっちも入り口よね。反対側だけど……)
南北に細長いこの公園には、北側と南側に出入り口があって、どちらにもたしかに屋台が出ている。
けれど、アイスクリームを売っている屋台は、こちら側ではなかった。
お祭りの日だけあって、店の数もいつもよりも多いし、入り口の近くは人も多い。
それでも屋台を眺め歩いた限りでは、綿菓子(コットンキャンディ)や色とりどりの砂糖菓子を売っている店はあっても、アイスクリームは見当たらない。
「あー、失敗したあ!」
公園を突っ切れば反対側の入り口もそんなに距離はない。
けれど躊躇われてしまう。だって、そのためにはヨシュアのいるベンチの前を過らなければならない。
あれだけきっぱり言って走り出したのに、まさか行き先を間違えちゃった、てへへ、と言えるだろうか──言えるわけがない! 恥ずかしすぎる。
![]()
まして、《黒の導力器(オーブメント)》を巡る一連の事件が解決し、遊撃士として成長したと思った矢先である。
ヨシュアがいないと心配、なんて言わせない──と大見得を切ったのに。
あの台詞はなんだったのか。
成長したと思ったし、自分の気持ちに気づいたからヨシュアに告白しようと……。
などと考えていたら頬が熱くなってきた。
きっとたぶん自分はいま真っ赤になっている。そうエステルは自覚できてしまう。
(絶対ダメ! こっちからなんて戻れないってば!)
仕方ない。ここは一度大通りに出て、反対側の入り口に回るとしよう。
屋台の群れと人混みを抜けて通りへと出る。
お祭りの賑わいを眺めつつ歩いた。
意外と時間がかかったのは、やはり人が多く歩いているからだ。
ただ反対側の公園の入り口まで来ると、その人波もやや落ち着いて、ちらほらと見かけるだけになる。
木々の緑を見ていて、ようやくエステルの気持ちも落ち着いてきた。
あまり考え過ぎないほうがいい。なるようにしかならないもの、と開き直りの気分を手に入れたと思ったら──。
「やめて! 手を放しなさいよ!」
小さな女の子の悲鳴が聞こえた。
公園のなかからだ!
悲鳴の聞こえたほうへと走る。
アイス屋があるかどうか確認するのも意識から吹っ飛んでいた。
大きな木の陰に隠れるようにして三人の男が輪になっていた。悲鳴はその輪のなかからあがったのだ。
「ちょっと、あんたたち!」
叫んで男たちの注意を引いてから、輪のなかへと飛び込む。
素早く状況確認。
小さな──たぶん、七、八歳くらいの女の子と男の子が一人ずついて、男の子の小さな腕が男の一人に掴まれている。
男たち三人は、三人とも体格の大きな青年だった。二十歳は越えてないと思うけれど、エステルよりは二、三歳上だろう。
全員が浮かれた柄のシャツをだらしなく着ていて、腰の革のベルトからは意味があるのかないのか判らないお揃いの銀の鎖をジャラジャラと提げていた。
(武器……? なのかな。それにしちゃ鎖が細くて強度が足りない。棍を叩きつけたら切れちゃいそうだし、あれで殴られたくらいじゃ痛いくらいで、なんとか耐えられる)
と考えそうになって、エステルは慌てて頭を振った。
すっかり遊撃士の思考になっている。
もちろんあれは流行りの装身具ってやつに違いない。シュミ悪いけど。
ルーアンの《レイヴン》の連中をちょっと思い出した。
「なんだ、てめぇはよう?」
男たちの一人、いちばん太った奴が、肩をいからせ、下から睨)め上げるようにしてエステルの顔を覗きこんでくる。
「あのね。なにをやってるのか聞いてるの」
「そのひとたち、レインのけいひんを取ったの!」
答えたのは女の子のほうだった。
「けいひん? あ、景品ね」
少年を掴んでいる男の、もう片方の手には、お祭りの屋台で売ってそうなおもちゃが握られている。木製の遊具だった。
エステルは呆れてしまう。
「あんたたちね……なに、子どものおもちゃ取ってるのよ」
「おかねになるのよ」
またも女の子が答える。
「は?」
「レインの当てたのは、すぺしゃるバージョンなの。すっごく珍しくて。ほら、縁のところが金色でしょ。あれ、百個に一個くらいしかなくて──」
「あー、はいはい」
あるある。子どもの頃にエステルも一時期はまったものだ。ガラス玉を転がして当てる遊びとか。まだ机の引き出しのなかにあるはずだ。それで、そういうおもちゃは、お祭りのときには、少しだけ大きいのとか、柄が珍しいのとか売っていて、それらは子どもたちの間では「特別」なものとして価値があった。
「だからってねぇ……」
あの程度のおもちゃなら、一個五十ミラも出せば買えるはずだ。新鮮なミルク一杯分くらい。いくら「特別」といっても、所詮は子どもの価値観の話である。
「売れば、二千ミラにはなるんですよ、お姉さん」
そこで初めて男の子のほうが口を開いた。
言われた言葉の意味が頭に染み込んできてびっくりしてしまう。
「は? え、ええ!? にせん~!」
霜降りヒレ肉のお食事二十回分じゃないの!? と咄嗟に換算してしまった自分の頭にエステルはちょっと自分のことながら動揺してしまった。
第9弾 『英雄伝説 閃の軌跡 04』さがら梨々メッセージイラスト
第8弾 『みんな集まれ!ファルコム学園(5)』
新久保だいすけメッセージイラスト
第7弾 『英雄伝説 閃の軌跡 03』さがら梨々メッセージイラスト
第6弾 『英雄伝説 閃の軌跡 02』さがら梨々メッセージイラスト
第5弾 書き下ろし短編「恋する乙女の日常」& YahaKoメッセージイラスト
『英雄伝説 閃の軌跡 メンタルクロスリンク』が発売したことを記念し、草薙アキ先生書き下ろしの特別短編をファルコムBOOKSサイト限定で掲載! 作中にもあった、トールズ士官学院の愛の狩人(?)マルガリータの、華麗なる一日とは? 一途に恋する乙女の日常を追ってみた!

「……ぐごご……ずぴー」
マルガリータの朝は早い。
「マルガリータさま、起床のお時間です」
もちろんメイドが、である。
導力式目覚ましがけたたましく鳴り響く室内で、メイドは顔色一つ変えず、自らの主人を起こそうとする。
が。
「……ふごごごご……ぐご……」
当の主人はまったく起きる気配を見せず、枕元に置かれた五つの導力式目覚ましだけが、哀愁を漂わせながら鐘を鳴らし続けていた。
「……さて」
もっとも、それはメイドにとって日常茶飯事――彼女は冷静に目覚ましを止めると、マルガリータのぷっくりとした鼻先に、先ほど焼いたパンを近づける。
「……ぐごご……ふごっ!? ふごふごっ!?」
ぴくぴくと鼻の穴を開いたり閉じたりさせた後、マルガリータは涎を垂らしながら瞳
![]()
を開けた。
「……あらぁん? なんだかいい匂いがするわぁん……」
すかさずパンを後ろ手で隠し、メイドは恭しく頭を垂れた。
「おはようございます、マルガリータさま。すでに朝食の用意は整っております」
「あら、おはよぉ。ならそろそろ起きようかしらぁ……ふわあ~っ」
眠気を絞り出すかの如く、マルガリータは大口で欠伸をし、身体を伸ばす。
瞬間、ぶちんっと寝間着のボタンが飛んでいった。
「……あらぁ? 今何か聞こえたかしらぁん?」
「気のせいでございましょう。それよりお召し物を」
「そうねぇ。じゃあお願いするわぁん」
「かしこまりました。では浴室の方に」
マルガリータが浴室に向かったことを確認したメイドは、すかさず乱れた寝具を直し、窓を開け、下着と制服一式を手にその後を追う。
マルガリータが浴室に着いた頃には、メイドも彼女のすぐ後ろに控えていた。
これはリィンたち《Ⅶ組》と、その仲間たちが〝騒動〟に巻き込まれている間、平行して行われていた、一人の恋する少女の物語である。
マルガリータ・ドレスデン。
ミリアムと同じ〝調理部〟に所属している、ドレスデン男爵家の令嬢であり、このトールズ士官学院には、主に〝花嫁修業〟と〝婿探し〟を目的に入学したという。
中でも、今マルガリータが熱を上げているのが、アリサのライバル的存在である、フェリスの兄――二年の貴族クラスに在籍している、フロラルド伯爵家のヴィンセントだ。
手作りのクッキーを届けたり、ラブレターを出したりと、猛アタックを続けているのだが、結果は言わずもがな、である。
とはいえ、マルガリータの方は、着実に心が揺れつつあると確信しているようだが……。
そんなマルガリータは、貴族用の白い制服に袖を通し、朝食にしては些かボリュームのある量の料理を口に運んでいた。
傍らには、先ほど方彼女を起こしたメイドの姿もある。
寝間着のボタンはすでに縫い付け、洗濯物として洗い済みだ。
「……はぁ、美味しかったわぁん」
マルガリータの食事が一段落したところで、メイドは本日の予定を彼女に尋ねる。
今日は自由行動日であるため、授業の類は行われていないのだ。
「マルガリータさま、本日はどのようにして過ごされますか?」
「ムフフン、決まってるでしょぉ♪ 今日も愛しのヴィンセントさまに、あたしの〝愛〟をお届けしないとぉん♪」
「承知いたしました。では早速包装用の小包とリボンをお持ちいたします」
「ええ、お願いねぇん」
メイドから小包とリボンを受け取ったマルガリータは、鞄を手に、その逞しい足でしっかりと大地を踏みしめながら、調理室のある本校舎二階へと赴く。
そこにはすでに調理部の部長であるニコラスや、《Ⅶ組》のメンバーであるミリアム、そして調理部の部員であろう生徒たちの姿がちらほらとあった。
マルガリータの姿を確認したミリアムは、いつものようににぱっと笑顔で手を振った。
「あ、おはよー、マルガリータ」
「あら、ガキンチョ。あなたもいたのねぇん」
「うん。マルガリータもお菓子作りに来たの?」
そう問われ、マルガリータは「当然よぉん!」と胸を張って答えた。
「愛しのヴィンセントさまが、あたしのクッキーを今か今かと待ち望んでいるのだものぉん!」
「あはは、じゃあボクと同じだね。よーし、ボクも頑張るぞー」
ぐっと拳を握り、ミリアムは足早に踵を返す。
マルガリータが鞄を調理台に置き、中を漁っていると、ふいに背後から声をかけられた。
「やあ、おはよう。今日もクッキーを作りに?」
七三に分けられた髪型に、糸目が特徴的な平民の生徒――部長のニコラスである。
リィンに料理手帳をあげたり、レシピを教えてくれたりと、面倒見のよい性格の少年だ。
「ええ、そうなのぉん。以前いただいた〝黒トカゲの尻尾〟と相性の良さそうな具材が、色々と見つかったのよぉ」
「それは何よりだよ。じゃあ怪我には気をつけてね」
「ええ、分かったわぁん」
ニコラスが去った後、マルガリータは自ら調合した具材こと〝液体〟の入った小瓶を鞄から取り出した。
地下水道にいる魔獣のような色彩の液体を、マルガリータは「ムフフン♪」と邪悪な笑みで見つめる。
このどう見ても怪しげな液体――その正体は、マルガリータ特製の〝惚れ薬〟である。
もちろんクッキーに混ぜるためのものだ。
絶世の美女を輩出したと言われるドレスデン男爵家の令嬢――マルガリータの魅力を以てすれば、このような代物を使わずとも、ヴィンセントのハートを射止めることは容易いであろう。
だが今のヴィンセントは、マルガリータの魅力にくらくらなのか、恥ずかしがって距離を取るばかり。
ならばその心を素直にさせるのもまた、将来の妻として与えられたマルガリータの役目――と、そんな感じで惚れ薬を仕込もうとしているのである。
ちなみに、ニコラスから譲り受けた〝黒トカゲの尻尾〟も、惚れ薬の材料として、古の東方で用いられていたのだとか。
「生地を丸めてっと♪」
ミリアムが鼻歌交じりに形を整えているその横で、マルガリータはオーダーメイドのエプロンを身につけ、ボールの中の生地をゆっくりとかき混ぜていた。
最中、マルガリータは小瓶のコルクをぽんっと外すと、やけに粘度の高い液体をどろりとボールに投入する。
柔らかい卵色だった生地が、次第に赤黒いような、かと思えば、黒緑のような色へと変貌していく。
次いで立ち上ったのは、鼻を摘みたくなるような刺激臭だった。
「うわぁ……」
思わず顰め面になるミリアムのことなどお構いなしで、マルガリータも生地の型を整えていく。
ニコラスや他の部員たちが窓の外に新鮮な空気を求める中、マルガリータ特製生地は、導力オーブンの中へと消えていった。
「さあ、後は待つだけよぉん♪」
嬉々として後片付けを始めるマルガリータと、彼女の様子(むしろオーブン)を心配そうに見つめる部員たち。
惚れ薬などの変な薬品さえ混ぜなければ、別段料理が下手というわけではないのだが、今は何を言ったところで、聞く耳を持ちはしないだろう。
室内の臭いが落ち着いた頃、導力オーブンがチンッと甲高い音を発した。
クッキー(?)が焼き上がったのだ。
『――っ!?』
あのオーブンを開けたらまた臭いが充満する――そう眉間をハの字にしていた部員たちだったが、なんと驚くことに、オーブンの中から鼻腔をくすぐるクッキーの香りが、ふんわりと漂ってくるではないか。
「あれー?」
これにはさすがのミリアムも驚いたらしく、口元に指先をあてながら、小首を傾げていた。
「ムフフン、さすがはあたし♪ 焼き加減もばっちりだわぁん♪」
部員たちが呆然とする中、ミトンでクッキーを取り出し、マルガリータは小包にそれを分けていく。
五枚程度が入る女の子らしい小包だ。
小包の口をリボンで結び、マルガリータは愛情たっぷりのプレゼントを完成させる。
「いい匂いだね。今までで一番いい出来じゃないかな?」
「ええ、今日のはいつにも増して自信作よぉん。まあどうしてもって言うなら、仕方ないから試食させてあげるわぁん」
「え、いいのかい?」
「もちろんよぉ。でもそれであたしに惚れてもダメよぉ? この身はもう愛しのヴィンセントさまだけのものなのだからぁああああああああああああん!」
くねくねと火照った顔で身体を捩らせた後、マルガリータは溢れる感情を抑えきれず、小包を手に「じゃああたしは行くわぁん!」と廊下に飛び出していった。
マルガリータが去った後、ニコラスは皿に残ったクッキーを一枚手に取る。
「ブチョー、本当に食べるの?」
ミリアムが一応止めに入るが、ニコラスは「もちろん」と頷いた。
「こんなにいい匂いがするんだから、きっと今回は美味しく出来てると思うしね。それに食べ物を粗末にするのはよくないことだから」
言って、ニコラスはクッキーをかじる。
二、三秒咀嚼した後、ニコラスは微笑みながら言った。
「――うん、これは酷い」
――どさり。
「ぶ、ブチョー!?」
青い顔で白目をむくニコラスは、その後保健室送りになったとかなんとか。
なお、このクッキーがヴィンセントの元に届いたかどうかは定かではない――。

第4弾 『みんな集まれ!ファルコム学園(4)』
新久保だいすけメッセージイラスト
第3弾 『英雄伝説 閃の軌跡1』さがら梨々メッセージイラスト
第2弾 短編「ある日の編集部」
『英雄伝説 空の軌跡リベール王国スナップショット2』発売記念
特別短編『ある日の編集部』掲載!
6月10日にファルコムBOOKS最新刊『英雄伝説 空の軌跡リベール王国スナップショット2』が発売したことを受け、はせがわみやび先生書き下ろしの短編を掲載! ナイアルとドロシーの凸凹コンビが単行本で見せている漫才劇(?)の雰囲気の一端をぜひ味わってほしい。この短編の完全版は『月刊ファルコムマガジン vol.53』に掲載予定なので、そちらもあわせてチェックしてみよう!

『ある日の編集部』
リベール通信社の編集部は、王都グランセルの南西にある。
編集部の入っている建物の向いはコーヒーハウスになっていて、締切に追われた記者たちが時にコーヒー片手にタイプを叩いていたりもする。そういうときに頼む料理といえばサンドイッチだけ。元々この食べ物は片手だけで食べられるように作られた──という説もあるくらいだ。ナイアルもよく頼んでいた。
だが、今は違う。
コーヒーの傍らには大盛りの冷たいパスタが鎮座している。
「ナイアルさん。今日はのんびりしてますね」
はす向かいのテーブルに座っている馴染みの客から言われ、ナイアル・バーンズは片目だけを瞑ってみせた。
「俺の仕事はぜんぶ終わったからな」
![]()
珍しく、と言えてしまうのが悔しいところだが、今回の『リベール通信』の記事は楽勝だった。締切の三日前には書きあげてしまい、相棒のドロシーの写真も滞りなく仕上がって、レイアウトも完璧。だからこそこうして大盛り冷製パスタを頼む余裕もある。日も伸びて暑くなってきたからさぞ美味しいことだろう。
──さあ、食うぞ!
「せんぱ~い!」
悪魔の声が聞こえた。
──空耳だ!
ナイアルは構わずにパスタにフォークを突き立てる。
細い銀のフォークをくるりと回せば冷たいスープと半熟卵の黄身の絡んだ細い麺が巻きついてくる。美味そうだ。
どこかに不幸な先輩とやらがいるらしいが、自分には関係ない、はずだ。
「ナイアルせんぱぁい!」
どん、と背中を叩かれて、ナイアルはむせた。パスタを口から噴き出してしまう。
「ぶふっ!」
「
先輩ってば、かわいい後輩を無視するのはよくないですよぅ」
「ごほっ! お、おまえは──なんなんだよ!」
振り返って睨みつける。
「なに、と言われても……。先輩の相棒にして、めいカメラマンのドロシーですが」
「自分でゆーなっての。迷うほうだろうが、おまえは!」
「ええだから、ちゃんとそのように。迷カメラマン、と」
──自覚あったのか!
そして何故にっこりと微笑んでいるのか。
「わたしの顔、なにか付いてます?」
「いや……」
明るい色のブラウンの髪、頭の後ろで束ねた黄色いリボン、鼻の上には小さな丸眼鏡が乗っている。少女というにはやや苦しくなった二十歳の、リベール通信社の天才カメラマンにして天災カメラマン、ドロシー・ハイアットだ。
割合的には天才が二で天災が八くらい。
「で、なんでおまえは、俺の至高のパスタタイムを邪魔しやがる」
「あー、そういえば昔から疑問なんですけど、究極と至高って、どっちのほうが上等なんでしょう?」
「なんだぁ? うーん。言葉ってのは文脈次第なところもあるからなぁ」
「あ、いえ、そんなことはどうでもいいんですってば」
「おまえが振った話題だろうが!」
「大変なんです!」
「それは聞いた」
「では、ちょー大変なんです!」
「……大変な内容を言ってくれ」
ナイアルは我慢した。
いちいち腹を立ててはドロシー・ハイアットと会話はできない。それに、こいつの言葉はあちこち迷走しているように見えて、時々妙に鋭かったりもする。油断できない。迷走しただけで終わることもあるのだが。だが天才の思考回路なんぞ、どこでどう繋がっているのか凡才のナイアルにはどうせ判りゃしないのだ。
「原稿に穴が開きました」
さらっと冷静に言われた言葉がナイアルの頭に染み込むまで、呼吸ひとつかふたつ分の時間が掛かった。
「あのー。聞こえてました?」
「俺は原稿を仕上げたよな?」
まさかあれは夢だったんじゃないだろうな?
「はい。ばっちりです。わたしの写真もいちばん可愛い子を採用していただいて──」
「それはどうでもいい」
「ぶー」
「ってことは、俺の原稿じゃないわけか」
その通りだった。ドロシーの言うことには、北の大国エレボニア帝国へと取材に飛んでいた記者が突然の腹痛で入院となったらしい。命には別状ないようだが、記事が丸々ひとつ空いてしまった。
「大変じゃねえか!」
「だからそー言いましたってば」
「おまえの顔が大変じゃなかったんだよ!」
「ええー? そんなにですかぁ?」
「のびきったこいつとおんなじ表情だった」
テーブルの上のでろんとなったパスタを指さしたら、ドロシーが微妙な顔つきになった。
「先輩がわたしをどー見ているかは、すっごくよく判りました」
「で、なんでそれを俺に言いに来た?」
察しはついたが敢えて聞く。できれば嫌な予感のまま終わって欲しい。
「穴埋めはおまえたちでやれと編集長が」
「おまえたち?」
ドロシーがナイアルを指さした。
指さしたまま微笑んだ。
その指を掴んでナイアルは無理やりドロシー自身のほうへと向ける。
「おーじょーぎわが悪いですよぅ」
「おまえが俺しか指ささねえからだ」
「だって、わたしは写真係ですし。記事は書けませんってば」
「あいつの記事は今号のメインだろうが。いったい何ワードあると思ってやがる!」
「記者のひとって単語数で長さを測りますよねー。それでよくぴったりに納められるものだと昔から感心していて」
「やかましい。無茶言うなって言ってんだ!」
「編集長が──」
ぎろりと睨んだら、ドロシーは口を閉じた。おずおずと上目遣いでナイアルのご機嫌を窺ってくる。ナイアルはちょっとだけ反省した。ここでドロシーを怒るのは筋が違う。それにどうせ怒っても事態は変わらない。
「編集長が何だって?」
先を促した。
「信頼している、と」
「そんなもの、犬にでも食わせちまえ!」
あの編集長、こういうときだけ持ち上げやがるのだ。ナイアルはその手には乗るかと思っていたが、どうせ逃げられない運命だとも判っていた。
地獄の三日間の始まりだった。
※この続きは『月刊ファルコムマガジンvol.53』にて!
第1弾 ファルコムブックス3周年お祝いコメント
日本ファルコム株式会社 代表取締役社長 近藤季洋
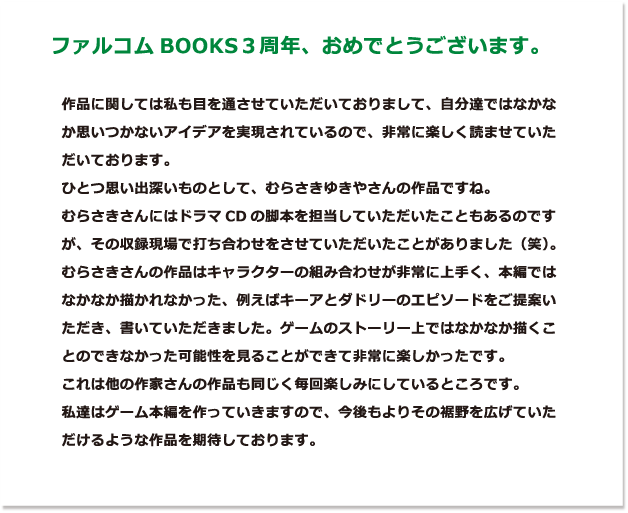
作家 はせがわみやび
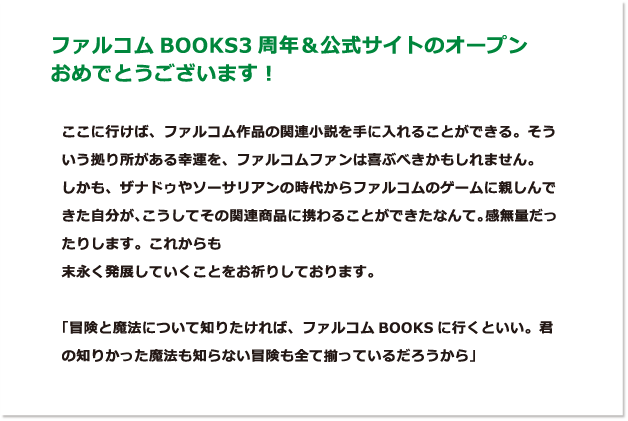
英雄伝説 空の軌跡 1 消えた飛行客船
英雄伝説 空の軌跡 2 黒のオーブメント
英雄伝説 空の軌跡 リベール王国スナップショット
英雄伝説 空の軌跡 リベール王国スナップショット2
株式会社キャラアニ プロデューサー 平賀忠和